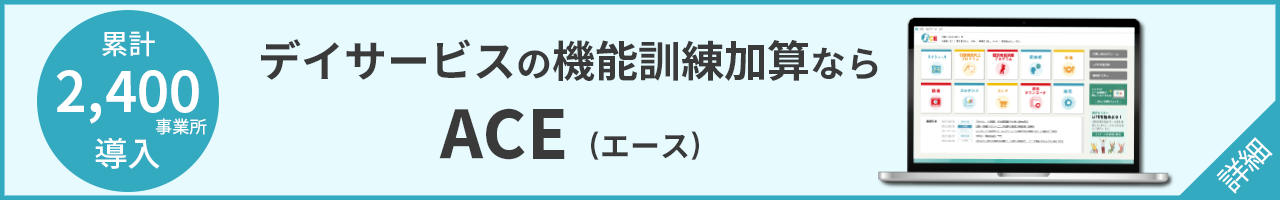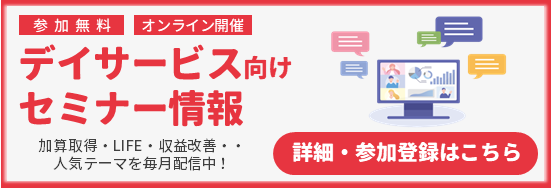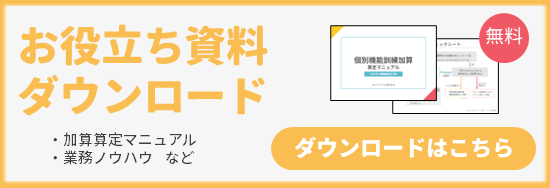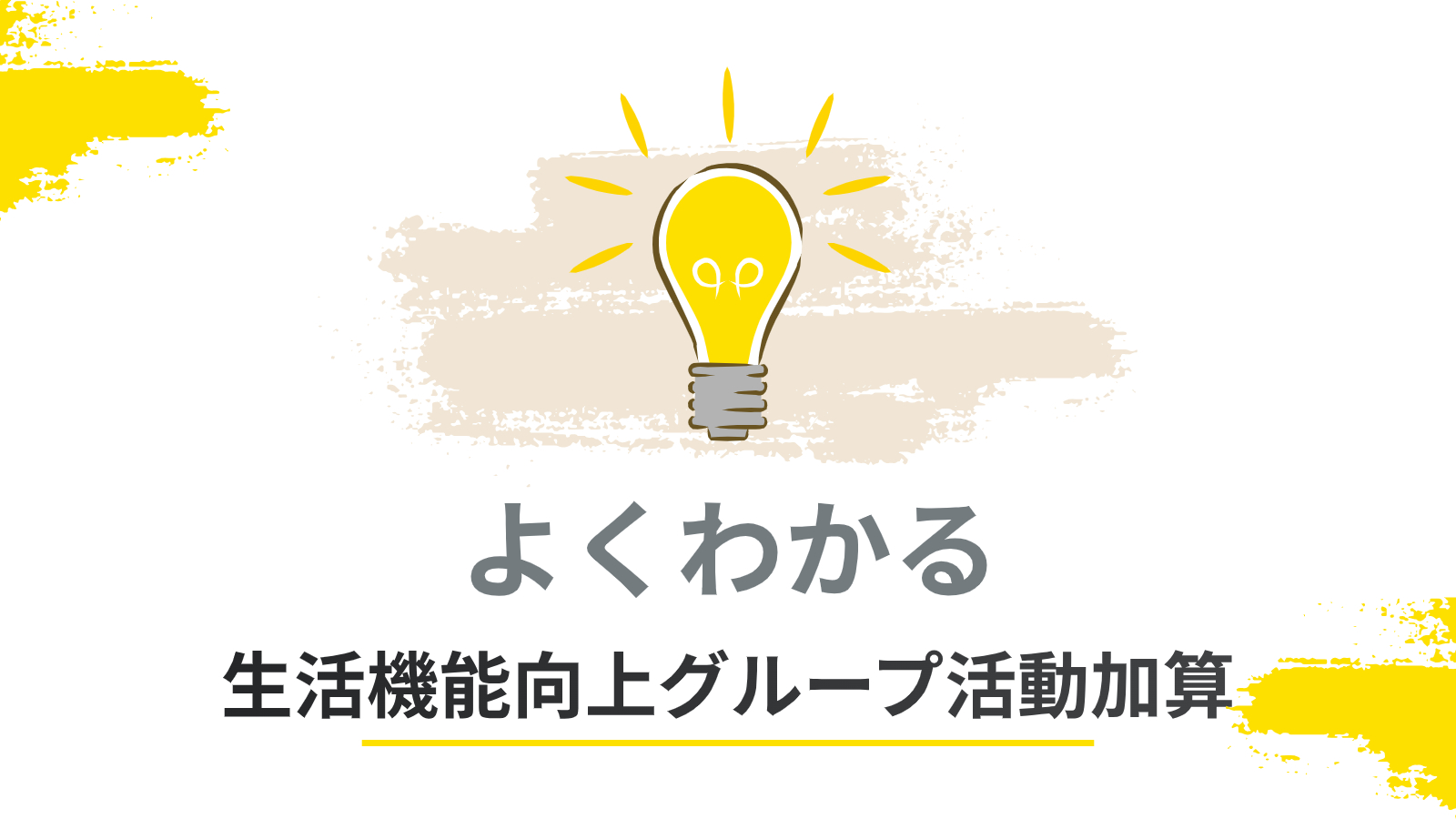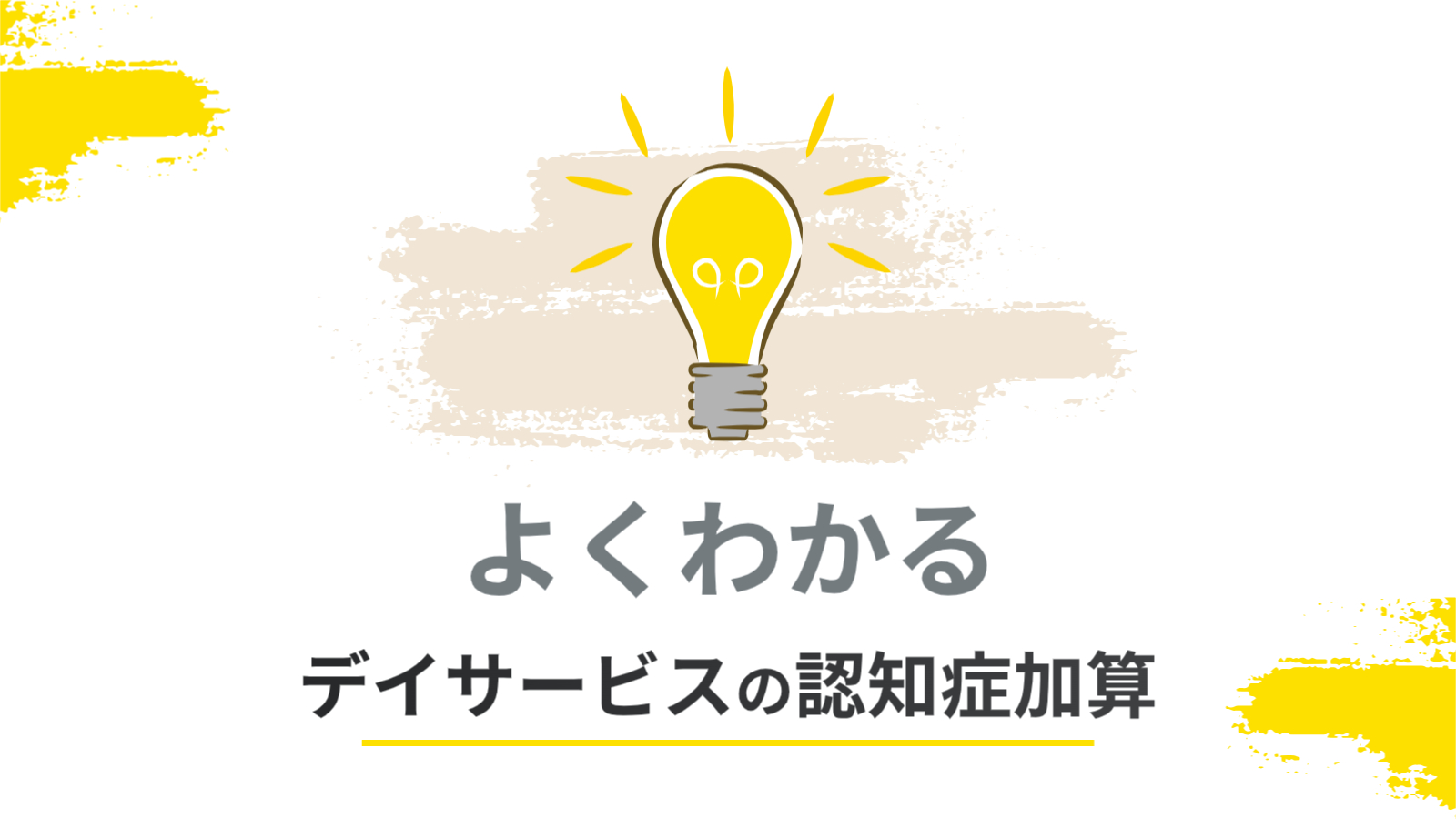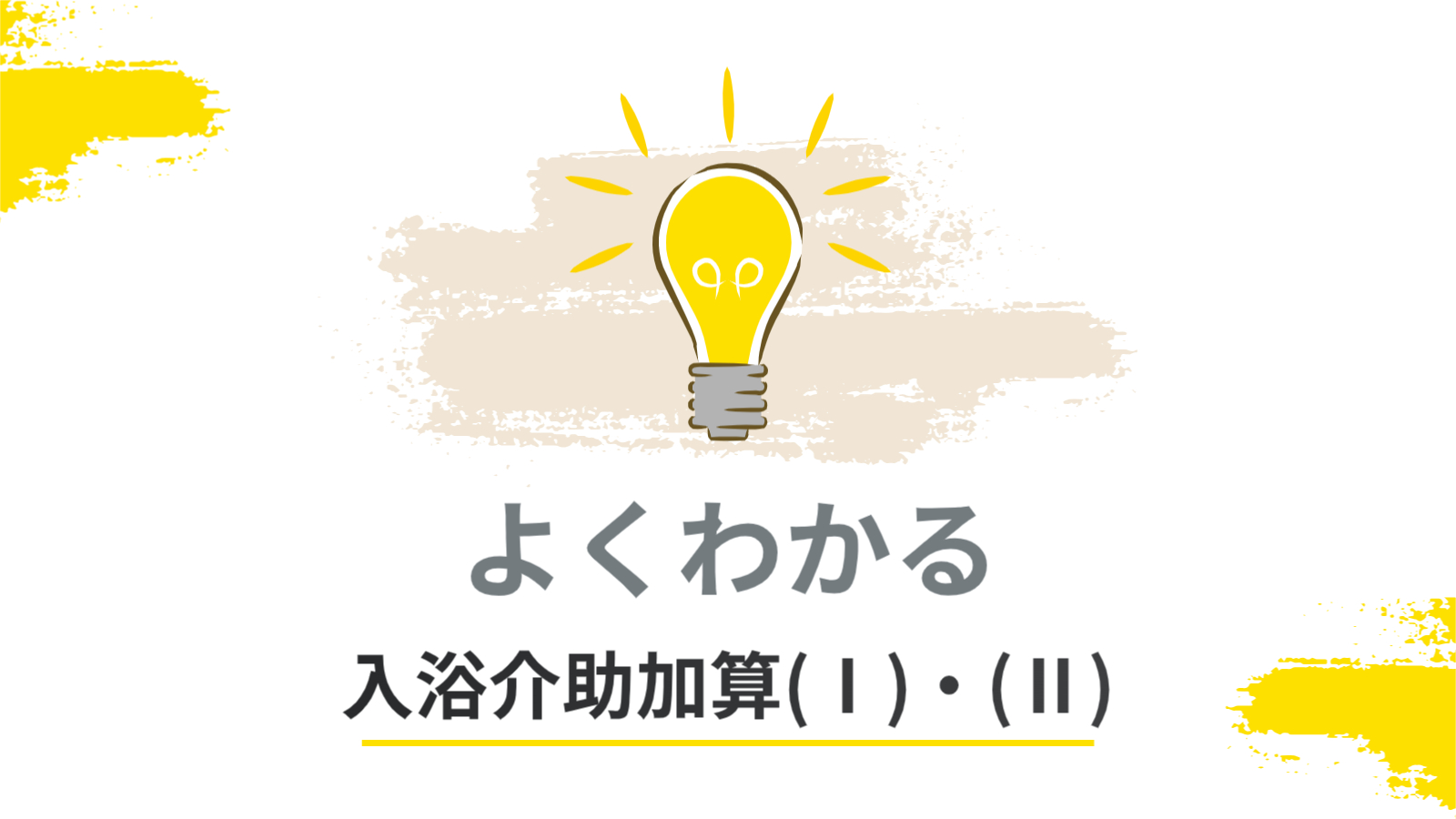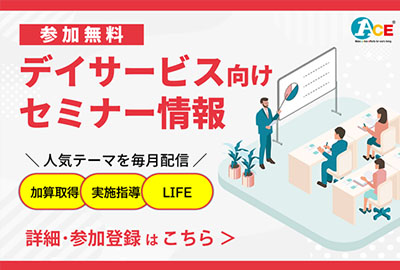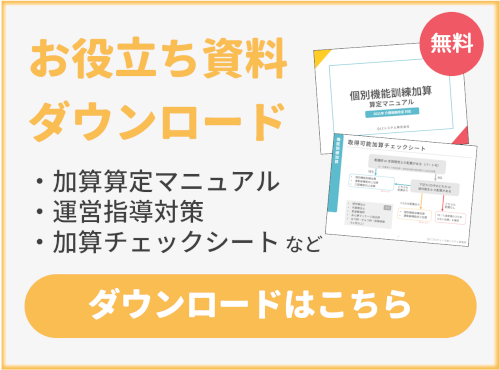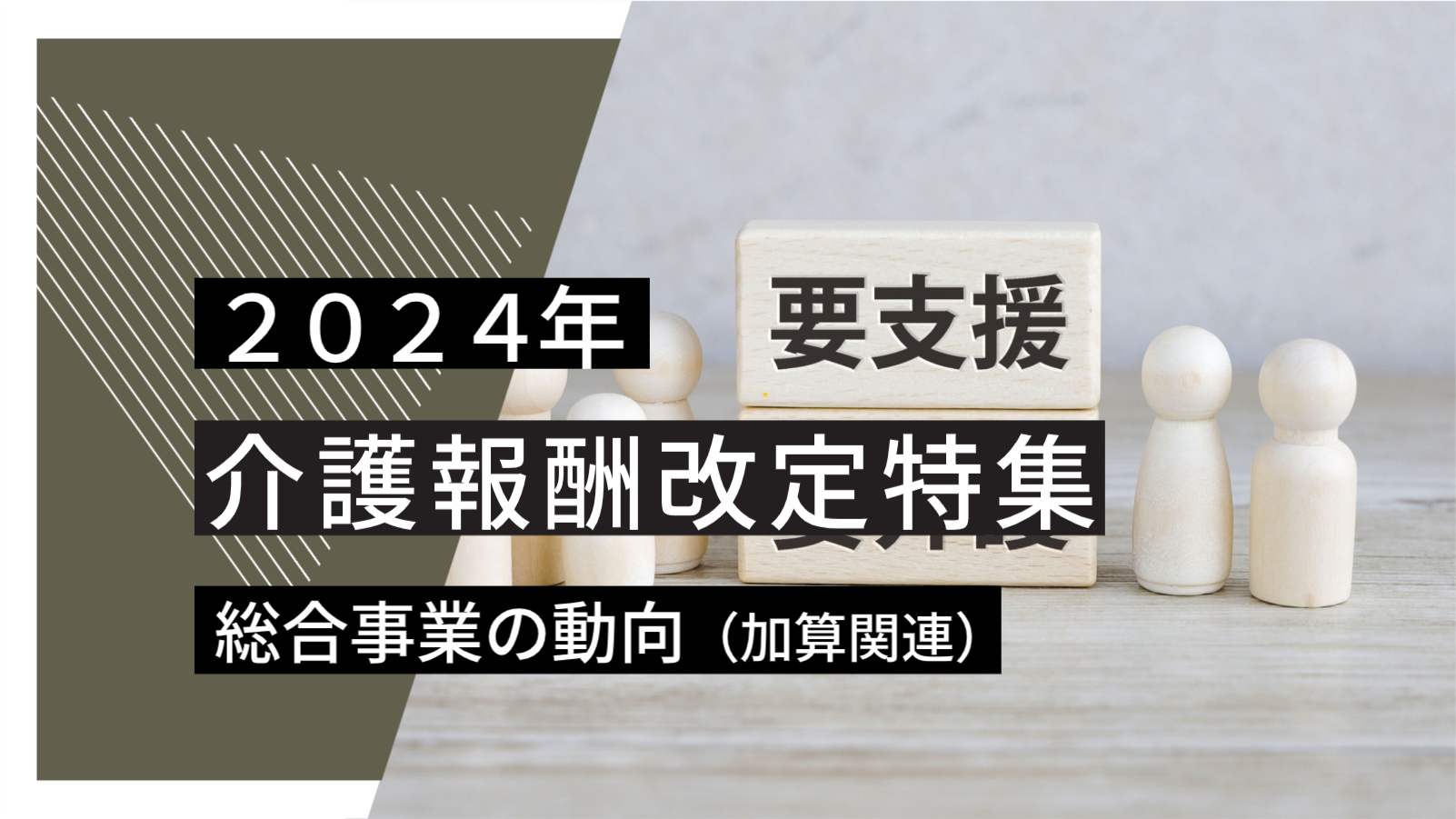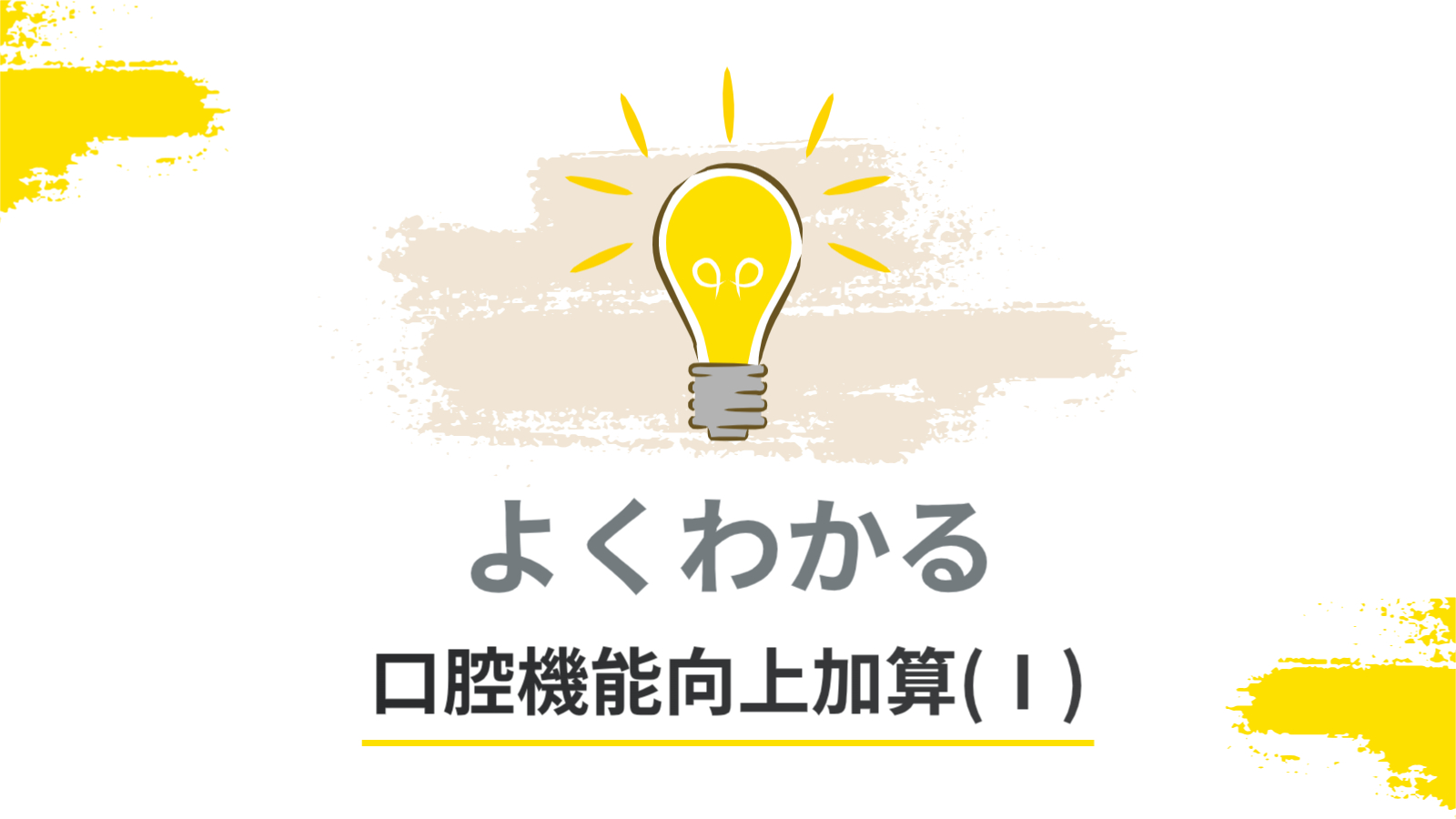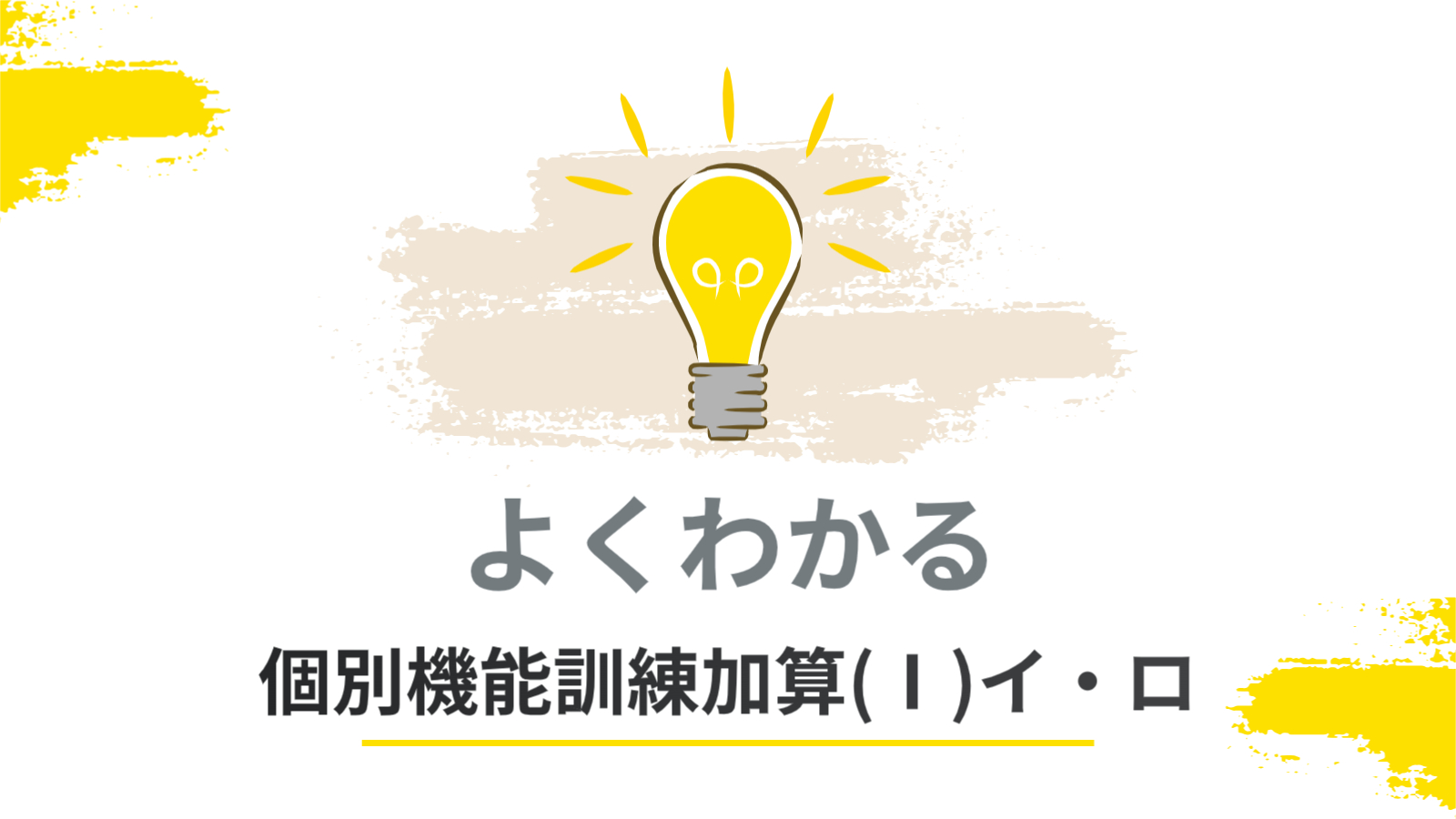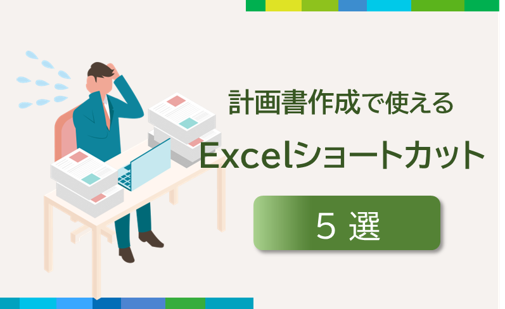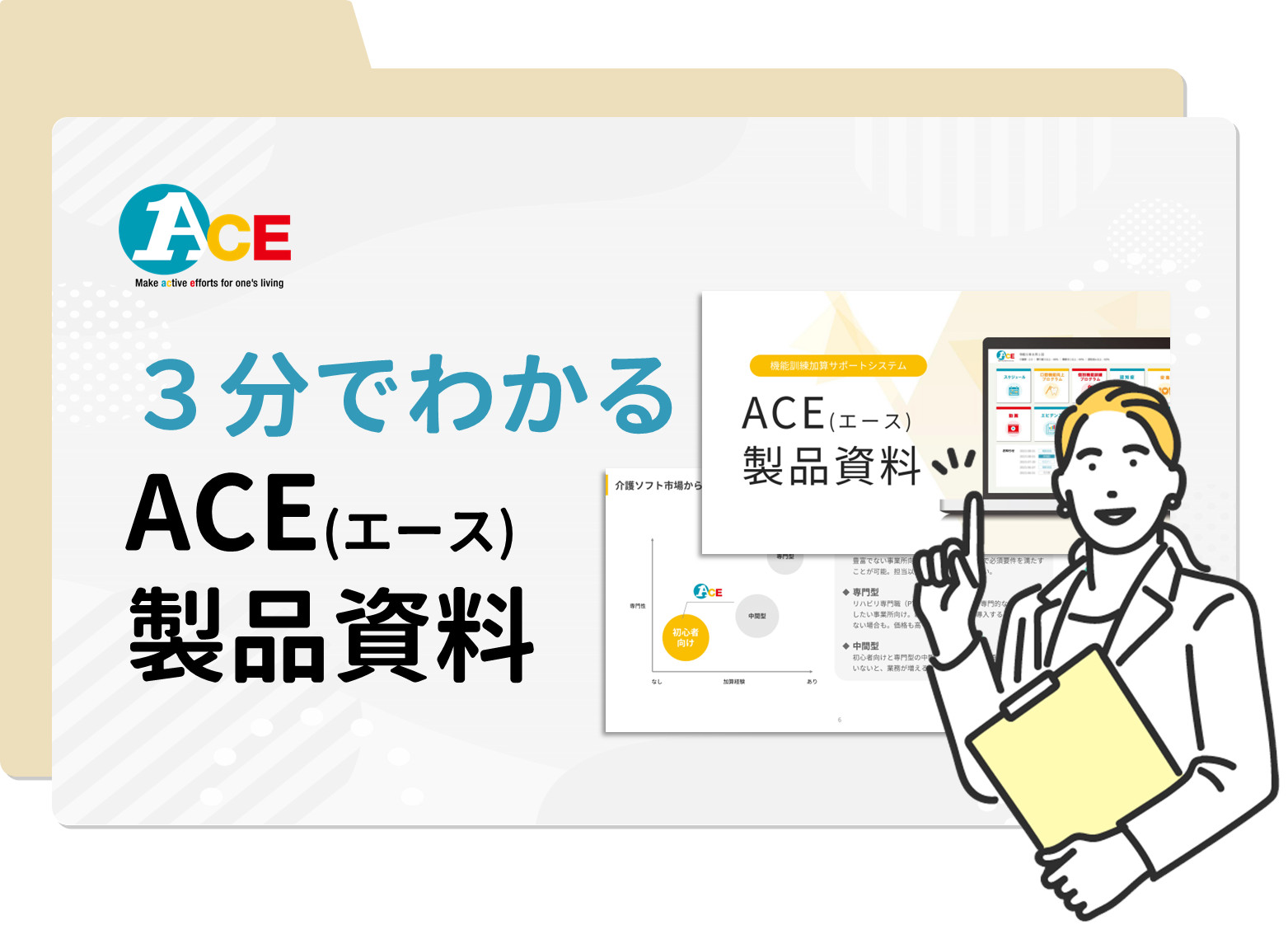【通所介護・デイサービス】
本ページは2021(令和3)年度報酬改定時に作成していますが、2024(令和6)年度改定でも内容は変更ありません。
生活機能向上連携加算とは、リハビリテーションを行う医療機関等の理学療法士等が共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することを評価する加算です。本ページでは、厚生労働省より掲示されている算定要件等をご紹介します。
詳細につきましては、届出を行う各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
生活機能向上連携加算の目的
生活機能向上連携加算は、利用者ができる限り自立した生活を送れるように、「自立支援・重度化防止」に資する介護を推進するため、生活機能向上を図ることが目的となっています。
| <事業所のメリット> |
| 事業所によってはリハビリ専門職がいない場合もあります。その場合、リハビリ専門職によるアドバイスが入ることで、自立支援や重度化防止へ向けて機能訓練に力を入れて取り組むことができます。 |
| <利用者のメリット> |
| 多少の自己負担は増えますが、リハビリ専門職はリハビリを指導するプロのため、的確なアドバイスを受けて訓練を実施することで、生活の質の向上が期待できます。 |
<通所介護>生活機能向上連携加算
単位・算定要件は以下の通りです。
| 名称 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
| 単位 | 100単位/月 ※3カ月に1回を限度 ※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可 |
200単位/月 ※個別機能訓練加算算定の場合、100単位/月 |
| 対象者 | 要支援(総合事業対象者)・要介護の利用者 ※介護予防は、各自治体によって単位数等が異なる場合があります。 |
|
| 算定要件 | 医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態(ADL・IADL等)を把握した上で助言を行う。
計画の内容や進捗状況を利用者・家族に説明する際にICTを活用して行うことも可能。※利用者等の同意が必要。 |
医療提供施設の理学療法士等が3カ月に1回以上、通所介護事業所を訪問して、助言を行う。 |
| 共通要件 | 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等からの助言を受け、機能訓練指導員等が共同してアセスメントを実施し、個別機能訓練計画の作成を行う。
機能訓練指導員等は各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者・家族に説明、理学療法士等に報告相談し、理学療法士等と共同で3カ月に1回以上必要に応じて計画の変更を行うこと。 ※理学療法士等=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師 |
|
留意点:個別機能訓練加算との併算定
個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)が100単位/月となります。
◆関連記事
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
生活機能向上連携加算はICT活用で算定可能
令和3年4月の介護報酬改定により、ICT活用により算定できる「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」が新設されました。
※「生活機能向上連携加算(Ⅱ)」は、ICT活用では算定できません。
■ ICTとは―
「Information and Communication Technology(インフォメーションアンドコミュニケーションテクノロジー)」の略で、「情報伝達技術」を意味します。IT(情報技術)との違いは、情報の伝達や共有の側面の意味合いが強く、コミュニケーションに重点が置かれている点。ITは技術そのものを指しますが、ICTはその技術の活用に焦点をあてたもので、テレビ電話等を含む電子的コミュニケーションツールが該当します。
| <ICT活用のメリット> |
|
介護現場におけるICTの活用でイメージしやすいものが、計画書等の利用者情報等の書類を紙ではなく、電子で作成保管することが挙げられます。 電子書類は、紙に比べて手間を軽減するメリットがあります。例えば、紙では書類の量が増えると探したり、書類作成に時間がかかったりします。電子書類の場合、テンプレートに従って入力することができ、時間や手間をカットできます。 |
要支援(総合事業)の場合
生活機能向上連携加算は、要支援の利用者も算定が可能です。
参考:厚労省「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚 生労働大臣が定める基準案について」
ただし、2024年度介護報酬改定にて「運動器機能向上加算」は多くの自治体で廃止(基本報酬に包括)となっています。
そのため、生活機能向上連携加算を算定する際の計画書については、各自治体にご確認ください。
加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。
リハビリ専門職がいなくても、安心・簡単に加算取得をスタートできます。
◎ACEメールマガジン登録受付中
デイサービスに関するセミナー・報酬改定情報・サービスのご紹介など、役に立つ情報を配信中!
無料でご登録いただけます。
>>登録はこちらから